小学校入学時はキモノだった
〔その26〕
平成7年10月号 第36号 中尾佐之吉
戦後50年、その間国内の諸制度も大きく変わったが、地域社会も様変わりである。その中でわれわれの衣食住など、生活様式の変化も著しい。
そこで、忘れかけようとしている戦前の衣食住のことを思い出してみることにした。まずは、着物のことについて…。

この頃では大人でも子どもでも、男も女も、家の中でも外でも着るものは皆、洋服である。近年、飛行機で外国へ多くの人が旅行されているが、服装は国内でのそれと変わらない。日本に来る外人の服装も日本人と大同小異、テレビに映る外国の方も服装は誰も同じに見える。この点から言えば、日本人は立派な国際人といえよう。
戦前といってももう50年以上も前である。しかし私にとってはついこの間のように思えるのだが…。この地方ではまだまだキモノが幅をきかせていた。特に家庭婦人がそうであった。
昭和17年(大東亜戦争が始まった翌年)5月、私の父や近所の方らが白石島へ旅行された時の記念写真があった。その末尾へ掲載したのがそれである(写真省略)。この写真で見ると、まだまたキモノを着ている人が多いことがわかる。そして年配の方までが洋服を着るようになったのは戦後のことであると想像できる。
日本で洋服を着るようになったのは、概ね明治維新後であるが、先ずは軍人であり警察官であった。さらに官吏であり官公立の学校の男の先生というところ。
明治17年には岡山師範学校(男子)の学生が服に、また、明治33年開校の第六高等学校生や中学生(旧制)も学生服になっていくが、小学校児童(男)が服を着るようになったのは岡山市内で大正10年頃とか。
私が今村小学校(御津郡)へ入学したのは大正12年であるが、当時はまだ田舎だからキモノであった。そして履物は草履である。2年生の時、村長の息子と転校してきた男の子が服を着てくるようになりびっくりする。同級生全員(男)が学童服になり、履物がゴム靴になったのは4年生の頃だったろうか。
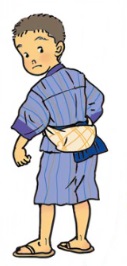
昭和の時代になると、学生はもとより一般人でも外で働く人は洋服に変わっていった。
そのような風潮のなかでも超然として「着物党」を堅持された方がいる。今村役場の長瀬芳太郎村長(明治45年~昭和6年在任)と貝原助役(大正13年~昭和20年在任)のお二人である在任中ずっとキモノであった。洋服を着たのを見たことがない。県庁や東京の内務省への陳情(水道敷設のことで上京しておられる)などにはどんな服装で出向いたのだろう。堂々、羽織・袴で乗り込んだのだろうか。聞いてみたいが、故人になっておられてはどうしようもない。
また、小学校の難波健治校長(明治38年~大正13年在任)もキモノ党であったようだ。ほかの男の先生方は洋服なのに校長先生はいつも和服だ。紀元節や天長節の式の時も羽織袴で教育勅語を奉読された。当時、来賓の長瀬村長も校長先生同様の服装であったのはいうまでもない。

その校長先生が大正7年にはほかの先生方と記念写真を撮っておられるが、その写真では「フロックコ-ト」を着ておられる(「今村史」掲載)。難波校長先生にもこういう時代があったのかと思い直す。それに大正3年の詰襟服での写真もあるから、根っからの「着物党」ではなかったのかもしれない。
戦後は、洋服オンリ-で、キモノは見限られたかの様相だが、男も女も外で働く時代で行動範囲も広くなってくるし、まして車社会では活動性のある服装が要求されるのは当然であろう。
家に居る時、蒸し暑い夏の季節には“ユカタがけ”でくつろぐという気分も悪くはないが、冷暖房の完備したこの頃では、いまさらと冷笑されそうだ。それでも町内の「夏まつり」に踊っている娘さんやお母さん方のユカタ姿は、まことにさわやかだ。洋服時代といってもこのような場所では、やはりキモノがふさわしく思える。
どのような時代になろうとも、キモノはすたらないに違いない。
