「君と僕」ことばはいつから
〔その34〕
平成9年10月号 第44号 中尾佐之吉
おさななじみの 想い出は
青いレモンの 味がする
閉じるまぶたの そのうらに
おさない姿の 君と僕
この歌詞は、永六輔さん作詞の「幼ななじみ」の一節でよく口ずさまれている歌だ。この詞の中の「君」と「僕」ということばは、いまではどこでも使われていて今さら取り上げて何を言おうとするのかと思われるかもしれない。これにも歴史がある訳で、前回の“さん”づけ、”ちゃん”づけを書いた以上、このことにも触れずにはおられないのである。
1.「君と僕」のことばは、この地方では私が子供の頃から
私が小学校へ入ったのは大正12年であるが、最初の頃は自分のことは“わし”、友だちは“おめえ”と言っていたと思う。村長の息子か転校してきた同級生が僕とか○○君とかいうことばを使うので、次第に皆が君・僕をつかうようになったと思う(註・小学校で3年生までは女の先生が担任であったから、男の子でも“さん”づけで呼ばれ、”君”づけで呼ばれることはなかった)。
私の父は学校の同級生だった友達を○○君と呼んでいたようだが、自分を僕と言っているのは聞いたことがない。また、近所の年配の人も当時、僕ということばは使わなかったように思う。
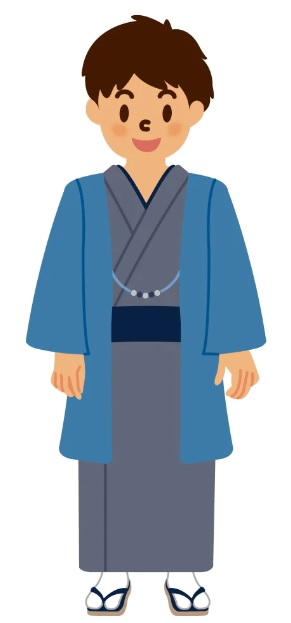
2.「君と僕」のことばを教わった“藤村”
島崎藤村著わす「生ひ立ちの記」によると明治5年(1872)長野県木曽郡で生まれた藤村が、明治14年9歳の時に上京して姉の婚家先へ寄寓し小学校へ転入することになる。
…私の故郷の習慣で他の朋輩を呼ぶには「わりゃ」と言ひ、自分のことはどんな目上の人の前でも「おれ」でしたが、その時都会の少年のやうに言葉遣ひを習ひ、「君」とか「僕」とかいふ言葉も姉からをそわりました。…と書かれている(註・… …内は、著書原文のままとし旧仮名遣いである)。
君と僕ということばは、東京の方では明治の初めにもう使われていたことが知られる。そうだとすると、このことばがこの地方まで普及するには何十年もかかっている訳で、新聞やラジオ・テレビなど情報通信の発達普及した現在では考えられないようなことだ。
3.君と僕のことばを明治以前に使った人がいる
幕藩時代、四民の最上位に君臨していた武士たちは、自分を「拙者」と言い、相手を「貴殿」と呼んでいたであろうと思うのだが、江戸末期、かの尊王の志士吉田松陰(1930~1859)は、そのようなことばを、ふだんは、あまり使わなかったらしい。
松陰は長州藩内はもとより他藩の人とも交際が広く、それらの人々と交わした大変多くの書簡を残しているが、その中で自分のことは「僕」と書いている場合が多く、同輩以下の相手には「君」ということばを使っている。例えば松陰が野山獄の獄中から9歳年下の門人高杉晋作(1839~1867)に宛てた手紙(安政6年)に「…僕は君に負き父に負くの人…」というような字句が見られる(註・君にそむき父にそむくの人とは、父や晋作の期待をうらぎり、当時の国法を犯してアメリカ行きを企て獄舎につながれるようになった自分という意味であろう)。
司馬遼太郎さんの「役人道について」という論文(文芸春秋所蔵)の中で


…桂小五郎(木戸孝允-1833~1877)は士分でありましたが、元来足軽身分とも言いがたかった時期の伊藤俊輔(伊藤博文―1841~1909)に対して「君と僕とは対等である」として上下の礼をとる必要がないといっている…
と書かれている。つまり、君と僕という表現はお互いが対等であり同志であることを意味していた訳である。
吉田松陰が使った君と僕ということばにもそのような思想が含まれていたに違いない。従って松陰門下生たちも同志の一人として、進んでこのことばを使ったことが想像される。

明治維新によって士・農・工・商という階級的身分社会が崩落し四民平等の社会になると、サムライだったからといって「おい、そこな町人※」などと呼び捨てにできないし、百姓・町人だからといって元士族を「おサムライさま」とたてまつる必要もなくなった。長州で発明された「君」と「僕」が新語として登場し、一般化するのも必然であったといえようか。(※司馬遼太郎著「風塵抄」P80)
今、当たり前のこととして使っている「君」と「僕」ということばも、維新時代の流行語(?)であったと、私は言ってみたいのである。ただし、国中に普及するには、相当の年月がかかったが…。
