


![]()

忠 魂 録(第二章)
![]()
|
母の像 強くきびしく やさしかった母 おかげで私がある お母さんありがとう 私たちのかなしみが くりかえされることの ないように 遺児 |
あれは、木の葉が舞う晩秋の寒い日の午後だった。 岡山護国神社の鳥居の外に英霊と向かい合う「母の像」に出会った。 周囲には人影もなく私はコートの襟を立て像の前に佇んでいた。いつしか胸が込み上げ頬に涙した。 『今一度訪れよう、そして、「四季折々の母と子の姿」と「忠魂録」をページに残そう』と。 明治維新以来幾度かの戦役事変に際し、祖国の隆昌を確信し散華された護国の英霊を心から敬仰し其の偉勲を顕彰し、ここにご事歴を留めます。 あれから63年、戦後の復興と今日の繁栄を驕ることなく、平和への感謝と行く末の平和を祈り謹んで英霊に捧げます。 平成20年2月 |
日清戦争
明治27年(1894年)7月から明治28年(1895年)4月にかけて行われた主に李氏朝鮮をめぐる日本と清朝中国の戦争。
開戦までの経緯
征韓論、明治政府成立直後から、朝鮮半島に対する経済進出を含む深い関心を抱いていおり朝鮮との国交渉を始めていた。
当時、朝鮮は鎖国状態で、国王高宗の父である大院君が政治の実権を握っていが対外政策では欧米諸国の侵入に厳しく反対し開国した日本も洋賊であるとし交渉が進まなかった。
こうした状況下の1873年、明治政府はその打開策として朝鮮への派兵を計画し、まずは西郷隆盛を中心とする使節を派遣するという征韓論を閣議決定した。
しかし、帰国した岩倉使節団の岩倉具視・大久保利通らがそれに反対し、決定が取り消された。これを明治六年政変(征韓論政変)という。
しかし征韓論に反対した大久保らも、朝鮮半島での武力行使の方針自体には反対ではなかった。
江華島事件
大久保らが実権を握っていた日本は1875年に江華島事件を起こして圧力をかけ、1876年に不平等条約である日朝修好条約(江華条約)を締結し、朝鮮を開国させた。朝鮮は当時清の冊封国であったが、この条約では冊封を近代的な意味での属国・保護国とは見做さなかったため、朝鮮は独立国として扱われた。
独立党と事大党の対立
江華島事件後の朝鮮では、急進的欧米化を進めようとする親日的な開化派と、漸進的改革を進めようとする親清的な守旧派との対立が激しくなっていった。それとともに、開化派を支援する日本と守旧派を支援する清との対立も表面化してきた。
壬午事変
1882年7月23日に壬午事変が起こり、清と日本の軍隊が朝鮮の首都である漢城に駐留することになった。日本の朝鮮駐留軍より清の駐留軍の方が勢力が強く、それを背景に守旧派が勢力を拡大していった。巻き返しを図った開化派は、日本の協力を背景に1884年にクーデターを起こし、一時政権を掌握した。
しかし、清の駐留軍が鎮圧に乗り出したため、日本軍は退却、クーデターは失敗した。
1885年に日本と清とは天津条約を締結、両国は軍を撤退させ、今後朝鮮に出兵する際にはお互いに事前通告することがさだめられた。
甲午農民戦争
1894年5月に朝鮮で、東学教団構成員の全琫準を指導者として民生改善と日・欧の侵出阻止を求める農民反乱である甲午農民戦争(東学党の乱)が起きた。朝鮮政府はこれを鎮圧するため、清に派兵を要求した。このとき、天津条約に従って日本側に派兵することを通知した。
日本は、その時政府と議会との激しい対立により政治的に行き詰まっていたが、対外的に強硬にでて事態打開をはかろうとした。加えて、清によるこれ以上の勢力拡大を恐れていたため、朝鮮政府からの派兵要請を受けていないにもかかわらず、壬午事変の結果締結された済物浦条約を根拠として公使館と在留邦人の保護のために1万人規模の大軍の出兵を決定した。事態の悪化にあわてた朝鮮政府は農民の要求をほぼ全面的に受け入れ、6月10日に停戦した。
日清戦争開戦
甲午農民戦争の停戦後、朝鮮政府は日清両軍の撤兵を要請したが、どちらも受け入れなかった。それどころか、日本は朝鮮の内政改革を求め、朝鮮政府や清がこれを拒否すると、7月23日に王宮を占拠して、親日政府を組織させた。清がこれに対して抗議して、対立が激化した。
日本は開戦に備えてイギリスの支持を得ようと条約改正の交渉を行い、7月16日に調印に成功した(日英通商航海条約)。この直後から日本政府は開戦に向けての作戦行動を開始し、7月25日豊島沖の海戦で、日清戦争が始まった。なお、宣戦布告は8月1日である。
なお、日本政府の強引な開戦工作に対して、明治天皇は「これは朕の戦争に非ず。大臣の戦争なり」との怒りを発していた。
戦争の経過
7月25日の豊島海戦の後、陸上でも7月29日成歓で日本軍は清国軍を破った。9月14日からの平壌の陸戦、9月17日の黄海海戦で日本軍が勝利し、その後朝鮮半島をほぼ制圧した。10月に入り、日本軍の第1軍が朝鮮と清との国境である鴨緑江を渡り、第2軍も遼東半島に上陸を開始した。11月には日本軍が遼東半島の旅順・大連を占領した。
1895年2月、清の北洋艦隊の基地である威海衛を日本軍が攻略し、3月には遼東半島を制圧、日本軍は台湾占領に向かった。
講和条約
開戦直後からイギリスは講和斡旋へ動き、清も1895年1月に講和使節を日本に派遣した。しかし、日本は遼東半島の完全占領を目指していたため、この講和条件を受け入れなかった。1895年3月下旬からアメリカの仲介で、日本側が伊藤博文と陸奥宗光、清国側が李鴻章を全権に下関で講和会議が開かれた。3月24日に李鴻章が日本人暴漢に狙撃される事件が起こり、このため3月30日に停戦に合意した。
4月17日日清講和条約が調印され、5月8日に清の芝罘で批准書の交換を行った。
条約の主な内容は次の通り
1、清は朝鮮の独立を認める。
2、清は遼東半島・台湾・澎湖諸島を日本に譲渡する。
3、清は賠償金2億両(テール:約3億円)を金で支払う。
このほかにもイギリスが清に要求して、まだ実現していなかった工場を建てる特権が含まれており、イギリスの立場を日本が代弁していた様子がある。
三国干渉とその後
当時ロシアは満州(中国東北部)への進出を狙っていたため、遼東半島が日本領になることに激しく反発した。このため、ドイツ・フランスとともに遼東半島を清に返還することを要求した。
日本政府には、列強三か国に対抗する力は無かったため、これを受け入れ、その代償として清から2億両を金で得た。以後、日本はロシアを仮想敵国として、清から得た賠償金で八幡製鉄所を建てるなど国力充実をはかった。
戦争後、欧米列強各国は清の弱体化を見て取り、中国分割に乗り出した。ロシアは旅順と大連、ドイツは膠州湾、フランスは広州湾、イギリスは九竜半島と威海衛を租借した。 台湾では、日本を快く思わない清朝の役人が、日本の統治を妨害するため、台湾人達を先導して台湾民主国を建国、日本軍と乙末戦争を戦ったが日本軍の優秀な装備と圧倒的兵力の前に敗北した。最終的に清朝の役人は資金を持ち逃げし、日本は台湾を征服し併合、台湾における植民地支配を開始した。
豊島沖海戦
7月25日、豊島沖で日本海軍第1遊撃隊は、清国軍艦「済遠」「広乙」と遭遇し、戦闘が始まった。優勢な日本海軍の応戦の前に「済遠」は逃亡を図る。
日本海軍の「吉野」「浪速」も、直ちに「済遠」を追撃する。その途上、清国軍艦「操江」及び汽船「高陞号」と遭遇した。「高陞号」は、戦争準備行動として仁川に清国兵約1100名を輸送中であった。第1遊撃隊司令官の命により「浪速」艦長の東郷平八郎大佐は「高陞号」に停船を命じて臨検を行い、清国兵が停戦命令に従わないため、「高陞号」を撃沈する。この時、英国人船員ら3人を救助し、約50人の清国兵を捕虜とした。
豊島沖海戦による、日本側の死傷者及び艦船の損害は皆無であった。他方、清国側には、「済遠」が大破し、「操江」は「秋津洲」に鹵獲され、「広乙」も破壊された。
なお、「高陞号」を撃沈したことによって、一時英国の世論が沸騰するが、英国が日本寄りの姿勢だった事もあり、イギリスの国際法の権威、ウェストレーキおよびホルランド博士によって国際法に則った処置であることがタイムズ紙をとおして伝わると、英国の世論も沈静化する。
成歓作戦・牙山作戦
6月9日に清国軍が牙城に上陸する。7月23日時点で4165名に達する。7月25日に朝鮮政府から大鳥圭介公使に対して、牙山の清国軍撃退が要請される。7月26日に第9歩兵旅団にその旨が伝達される。7月29日に日本軍は牙城に篭る清国兵を攻撃する。午前2時に、清国兵の襲撃により松崎直臣陸軍歩兵大尉ほかが戦死する。
午前7時に日本第9旅団は成歓の敵陣地を制圧する。
両作戦の日本側の死傷者は82名なの対して、清国兵は500名以上の死傷者を出し、武器等を放棄して平壌まで逃亡する。
なお安城渡の戦闘で第21連隊の木口小平二等卒は死んでもラッパを離さずに吹き続けたという逸話が残る。
平壌作戦
8月に清国軍は平壌に1万2千名の兵員を集中させる。9月15日に日本軍が攻撃を開始する。攻略に当たっていた日本軍の歩兵第18連隊長佐藤正大佐は銃弾を受け左足切断の重傷を負う。同日午後4時40分に清国軍は白旗を掲げて翌日の開城を約した。ところが、清国軍は約を違えて逃亡を図る。同日夜に日本軍が入城する
黄海海戦
黄海上で遭遇した日清艦隊は、9月17日12時50分に「定遠」から攻撃が開始される。日本側は連合艦隊司令長官伊東祐亨中条率いる旗艦「松島」以下8隻と第一遊撃隊司令長官坪井航三少将率いる旗艦「吉野」以下4隻であるのに対して、清国艦隊は丁汝昌提督率いる「定遠」「鎮遠」等14隻と水雷艇4隻であった。日本艦隊は、清国「超勇」「致遠」「経遠」等5隻を撃沈し、6隻を大中破「揚威」「広甲」を擱座させる。日本側は4隻の大中破を出し、旗艦「松島」の戦死者の中には勇敢なる水兵と謳われた三浦虎次郎三等水兵もいる。
この海戦で日本側が勝利したことによって、清国艦隊は威海衛に閉じこもることとなり、日本海軍は黄海・朝鮮の制海権を確保した。
鴨緑江作戦
10月25日払暁に、山形有朋率いる第1軍主力は渡河作戦を開始した。日本軍の猛勢に恐れをなした清国軍は我先にと逃走を図り、日本軍は九連城を無血で制圧する。この作戦成功により、日本軍は初めて清国領土を占領する。
旅順攻略戦
10月24日に大山巌大将率いる第2軍が金州に上陸する。11月6日に金州城を占領する。11月21日に、日本軍1万5千は清国1万3千弱に対して攻撃をする。清国軍の士気は極めて低く、堅固な旅順要塞は僅か1日で陥落することとなる。
日本側の損害は戦死40名、戦傷241名、行方不明7名に対して、清国は4500名の戦死、捕虜600名を出して敗退する。
攻略そのものは問題なかったが、その後の占領において大きな問題が発生した。『タイムズ』(1894年11月28日付)や『ニューヨーク・ワールド』(同年12月12日付)により、「旅順陥落の翌日から四日間、非戦闘員・婦女・幼児などを日本軍が虐殺した」と報じられたのである。虐殺された人数については諸説あるが、実際に従軍し直接見聞した有賀長雄は清国民間人の巻き添えが有ったことを示唆している。現在、この事件は旅順虐殺事件として知られている。
この事件は外交的に大きな影響をもたらした。当時はアメリカと不平等条約改正を交渉中の最中であり、この事件により一時アメリカ上院には条約改正は時期尚早という声が大きくなり、重要な外交懸案が危殆に瀕した。陸奥宗光はこのため『ニューヨーク・ワールド』に弁明せざるを得なくなる事態に陥ることとなった。
山東作戦・威海衛作戦
1月20日に日本陸軍は栄城湾に上陸する。行軍中に歩兵第11旅団長大寺安純少将が戦死する。2月2日に威海衛を占領する。
2月5日午前3時20分に威海衛港内に侵入した日本水雷部隊は清国の「定遠」を大破、「来遠」「威遠」等3隻を撃沈した。2月9日に「靖遠」を撃沈、「定遠」は自沈する。2月12日に丁汝昌提督は将兵の助命を日本側に懇願して自決をする。伊東司令長官は、鹵獲艦船の中から商船康済号を外し、丁汝昌提督の亡骸を最大の礼遇を以て扱い、丁汝昌提督の最期の希望を聞き届け、清国兵を助命する。このことは、通常例を見ない厚遇であった。このエピソードは海軍軍人の手本として全世界に伝わり、現在でもフェアプレイ精神の例として日露戦争の上村彦之丞提督とともに、各国海軍の教本に掲載されていると云う。
日本軍の損害
陸軍の兵士の主食は白米であったため脚気の患者約4万人、脚気の病死者は数千人で、陸軍の戦死者は数百人と戦死者より脚気で病死した兵士のほうが多かった。これは、当時脚気の原因が解明されておらず、陸軍軍医制度を確立した石黒忠悳や陸軍軍医総監であった森林太郎が脚気の原因は細菌であるという伝染病説に固執していたことなどによる。海軍では、脚気による死者はほとんどいなかった。ちなみに、海軍軍人、兵隊の主な食料は玄米であった。
だが、日清戦争当時は補給路が確立されておらず、兵站が滞ることがしばしばであった。平壌の戦いでは野津師団長以下が本国では乞食でさえ食わないという黒粟や玄米などで飢えをしのぐ場面が度々であった。
当時の日本陸軍は、まだしっかりした冬季装備と厳寒地における正しい防寒方法を持っておらず、結果として冬季の戦闘で多くの将兵が凍傷にかかり、相当な戦力低下を招いた。日清戦争後、この教訓を基にして防寒具研究と冬季訓練が行われるようになった。そうしたさなかに発生したのが八甲田雪中行軍遭難事件である。
村田銃による小銃企画の統一
欧米の軍事的脅威を感じた日清両国は欧米からの武器輸入を進めていた。だが、各軍がそれぞれの基準によってバラバラに輸入を行ったために、さまざまな国籍・形式のものが混在してしまい、弾薬の補給やメンテナンス面でも支障をきたしていた。
明治13年(1880年)、日本陸軍の村田経芳が日本で最初の国産小銃の開発に成功する。陸軍はこれを村田銃と命名して全軍の小銃の切り替えを進めた。その後、同銃は改良を進めながら全軍に支給されていった。日清戦争当時、村田銃の最新型が全軍に行き渡っていたわけではなかったが、弾薬や主要部品に関しては新旧の村田銃の間での互換性が成り立っていたため、弾薬などの大量生産が行われて効率的な補給が可能となった。
一方、依然として小銃の混在状態が続いていた清国陸軍では、部品の補給などに手間取ってしまうなどの混乱が生じてしまい、日本軍の攻勢を食い止めるだけの火力を揃える事が出来なかった。
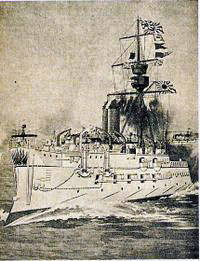 |
| 戦艦松島 |
北清事変
日清戦争後世界列強は、いずれも争って清国に経済的進出を計り始めた。特に鉄道の新設、工場の設置等は著しいものがあった。
明治33年膠済鉄道敷設反対が端を発し5月30日以来清国各地に議和団匪が群起した。この原因は清国民の外国に対する圧力に対抗する意識から発するものであった。
そこで、日・英・仏・伊の諸国は連合軍を組織し居留民保護のため即時出兵し団匪を平定した。
これは清国政府の了解のもとに行われたことであって短日月に終了した。
日露戦争
明治37年(1904年)2月6日から明治38年(1905年)9月5日は、大日本帝国とロシア帝国との間で朝鮮半島と中国満州(現在の中国東北部)を主戦場として発生した戦争。
日英同盟
ロシア帝国は、不凍港を求めて南下政策を採用し、露土戦争などの勝利によってバルカン半島における大きな地歩を獲得した。ロシアの影響力の増大を警戒するドイツ帝国の宰相ビスマルクは列強の代表を集めてベルリン会議を主催し、露土戦争の講和条約であるサン・ステファノ条約の破棄とベルリン条約の締結に成功した。これによりロシアはバルカン半島での南下政策を断念し、進出の矛先を極東地域に向けることになった。
近代国家の建設を急ぐ日本では、朝鮮半島を自国の独占的な勢力下におく必要があるとの意見が大勢を占めていた。朝鮮を属国としていた清との日清戦争に勝利し、朝鮮半島への影響力を排除したものの、中国への進出を目論むロシア、フランス、ドイツからの三国干渉によって、下関条約で割譲を受けた遼東半島は清に返還された。世論においてはロシアとの戦争も辞さずという強硬な意見も出たが、当時の日本には列強諸国と戦えるだけの力は無く、政府内では伊藤博文ら戦争回避派が主流を占めた。ところがロシアは、日本が手放した遼東半島の南端に位置する旅順・大連を1898年に租借し、旅順に旅順艦隊(第一太平洋艦隊)を配置するなど、満州への進出を押し進めていった。
1900年にロシアは清で発生した議和団事変の混乱収拾を名目に満州へ侵攻し、全土を占領下に置いた。ロシアは満州の植民地化を既定事実化しようとしたが、日英米がこれに抗議しロシアは撤兵を約束した。ところがロシアは履行期限を過ぎても撤退を行わず駐留軍の増強を図った。ロシアの南下が自国の権益と衝突すると考えたイギリスは危機感を募らせ、1902年に長年墨守していた孤立政策を捨て、日本との同盟に踏み切った。日本政府内では小村寿太郎、桂太郎、山縣有らの対露主戦派と、伊藤博文、井上馨ら戦争回避派との論争が続き、民間においても日露開戦を唱えた戸水寛人ら七博士の意見書や、万朝報紙上での幸徳秋水の非戦論といった議論が発生していた。
1903年4月21日に京都にあった山縣の別荘・無鄰庵で伊藤・山縣・桂・小村による「無鄰庵会談」が開催されたが物別れに終わった。桂は後にこの会談で日露開戦の覚悟が定まったと書いているが、実際の記録類ではむしろ伊藤の慎重論が優勢であったようで、後の日露交渉に反映されることになる。
直前交渉
1903年8月からの日露交渉において、日本側は朝鮮半島を日本、満州をロシアの支配下に置くという妥協案、いわゆる満韓交換論をロシア側へ提案した。しかし、積極的な主戦論を主張していたロシア海軍や関東州総督のエブゲーニイ・アレクセーフらは、朝鮮半島でも増えつつあったロシアの利権を妨害される恐れのある妥協案に興味を示さなかった。さらにニコライ二世や陸軍大臣アレクセイ・クロバトキンも主戦論に同調した。首相セルゲイ・ヴィッテの戦争回避論は退けられ、日本側への返答として朝鮮半島の北緯39度以北を中立地帯とし、軍事目的での利用を禁ずるという提案を行った。
日本側では、この提案では朝鮮が事実上ロシアの支配下となり、日本の独立も危機的な状況になりかねないと判断した。またシベリア鉄道が複線化されるとヨーロッパに配備されているロシア軍の極東方面への派遣が容易となるので、その前の対露開戦へと国論が傾いた。そして1904年2月6日、日本の外務大臣小村寿太郎は当時のロシア公使ローゼンを外務省に呼び、国交断絶を言い渡した。
ロシア側にとって、この通告がいかに突然であったかを知るには、ローゼン公使の対応を見てもわかるが、ローゼン自身もこれだけ日本に対して傲慢で挑発的な外交を展開しつつも、戦争が起きるとは想像していなかったらしく、この国交断絶通告を受け取った際、「この通告が戦争を意味するものか」と小村寿太郎に聞いた。ニコライ2世も「わがロシア帝国と日本との戦争は有り得ない。なぜなら朕がそれを欲しないから。」と放言し、日本は如何なる屈辱を受けてもロシアの前にひれ伏すだろうと考えていたという。これに対し、小村寿太郎は「この行為は戦争を意味するものではない」と返答。この返答は、国際法上の解釈から言えば違法と言えるものではないが、この状態ではどの外交ルートもあるわけではなく、実質的には戦争開始の通告である。かくしてニコライ2世は、1904年2月10日、アレクセーエフに対し日本との戦闘行為を容認。戦争を決断した。
各国の思惑
南アジアおよび清に権益を持つイギリスは日英同盟に基づき日本への軍事、経済的支援を与えた。露仏同盟を結びロシアへ資本を投下していたフランスと、ヴィルヘルム2世とニコライ2世とが縁戚関係にあるドイツは心情的にはロシア側であったが具体的な支援は行っていない。
開戦時の両軍の基本戦略
<日本側 >
陸軍は第一軍で朝鮮半島へ上陸、鴨緑江を渡河しつつ、在朝鮮のロシア軍と第一会戦を交えた後に満州へ進撃。第二軍をもって遼東半島へ橋頭堡を立て旅順を孤立させる。そののち、満州平野にて第三軍、第四軍を加えた四個軍でもって、ロシア軍主力を早めに殲滅する。のちに沿海州へ進撃し、ウラジオストックの攻略まで想定。海軍は旅順及びウラジオストックにいるロシア太平洋艦隊を黄海上にて殲滅した後に、ヨーロッパより回航してくるバルチック艦隊と決戦し、殲滅する。
<ロシア側 >
黄海の制海権確保の前提に基づき、日本側の上陸を朝鮮半島南部と想定。鴨緑江付近に軍を集結させ、北上する日本軍を迎撃させる。失敗した場合は日本軍を引き付けて、順次ハルビンまで後退して、補給線の延びきった日本軍を殲滅するという戦略に変わる。
開戦
日露戦争の戦闘は、1904年2月8日、旅順港に配備されていたロシア旅順艦隊に対する日本海軍駆逐艦の奇襲攻撃に始まった。この攻撃ではロシアの戦艦に損傷を与えたが大きな戦果はなかった。同日、日本陸軍先遣部隊の第12師団木越旅団が朝鮮の仁川に上陸した。瓜生外吉少将率いる日本海軍第三艦隊の巡洋艦群は、同旅団の護衛を終えたのち、2月9日、仁川港外にて同地に派遣されていたロシア巡洋艦のワリヤーグとコレーツを攻撃し損傷を与えた。2月10日には日本政府からロシア政府への宣戦布告がなされた。
ロシア旅順艦隊は日本の連合艦隊との正面決戦を避けて旅順港に待機した。もしロシアのバルチック艦隊が極東に回航して旅順艦隊と合流すれば戦力は圧倒的となり、制海権はロシアに奪われることになる。連合艦隊は2月から5月にかけて、旅順港の出入り口に古い船舶を沈めて封鎖しようとしたが、失敗に終わった。4月13日、連合艦隊の敷設した機雷が旅順艦隊の戦艦ペトロパブロフスクを撃沈、旅順艦隊司令長官マカロフ中将を戦死させるという戦果を上げたが、5月15日には逆に日本海軍の戦艦「八島」と「初瀬」がロシアの機雷によって撃沈される。一方で、ウラジオストックに配備されていたロシアの巡洋艦隊は、積極的に出撃して通商破壊戦を展開する。4月25日には日本軍の輸送艦金州丸を撃沈するなど、日本近海を縦横無尽に行き来し、これを追う日本の上村中将率いる第二艦隊を右往左往させ、船舶による補給に頼る日本軍を悩ませた。
黄海海戦・遼陽会戦
黒木為楨大将率いる日本陸軍の第一軍は朝鮮半島に上陸し、4月30日から5月1日、安東近郊の鴨緑江岸でロシア軍を破った。続いて奥保鞏大将率いる第二軍が遼東半島の塩大墺に上陸し、5月26日、旅順半島の付け根にある南山のロシア軍陣地を攻略した。南山は旅順要塞のような本格的要塞ではなかったが堅固な陣地で、第二軍は死傷者4,000の損害を受けた。東京の大本営は損害の大きさに驚愕し、桁を一つ間違えたのではないかと疑ったという。第二軍は大連占領後、第一師団を残し、遼陽を目指して北上した。6月14日、旅順援護のため南下してきたロシア軍部隊を得利寺の戦いで撃退、7月23日には大石橋の戦いで勝利した。
6月6日、乃木希典大将率いる第三軍が大連に上陸。7月末から海軍陸戦重砲隊が旅順要塞への砲撃を開始した。これを受けて旅順艦隊は旅順から出撃、8月10日、東郷平八郎大将率いる連合艦隊との間で黄海海戦となった。この海戦で連合艦隊は旅順艦隊の巡洋艦3隻他を撃沈したが、主力艦を撃沈することはできなかった。そのころロシアのウラジオストック艦隊は、6月15日に輸送船常陸丸を撃沈するなど活発な通商破壊戦を続けていた。8月14日、植村彦之丞中将率いる日本海軍第二艦隊は蔚山沖でようやくウラジオストク艦隊を捕捉し、大損害を与えその後の活動を阻止した。8月19日、第三軍は旅順攻囲戦の第一回総攻撃を開始した。だがロシアの近代的要塞の前に死傷者1万5,000という大きな損害を受け失敗に終わる。
8月末、日本の第一軍、第二軍および野津道貫大将率いる第四軍は、満州の戦略拠点遼陽へ迫った。8月24日から9月4日の遼陽会戦では、第二軍が南側から正面攻撃をかけ、第一軍が東側の山地を迂回し背後へ進撃した。ロシア軍の司令官クロバトキン大将は全軍を撤退させ、日本軍は遼陽を占領したもののロシア軍の撃破には失敗した。10月9日から10月20日にロシア軍は攻勢に出るが、日本軍の防御の前に失敗に終わる。こののち、両軍は遼陽と奉天の中間付近を流れる沙河の線で対陣に入った。
旅順攻略・奉天会戦
第三軍は旅順攻囲戦を続行中であったが、旅順要塞に対する10月26日からの第二回総攻撃は失敗し、11月26日からの第三回総攻撃も苦戦に陥る。戦況を懸念した満州軍総参謀長児玉源太郎大将は、大山巌元帥の指示を受け旅順方面へ着任。攻撃目標を要塞北西の203高地に絞り込む。日露両軍ともに戦死5,000、戦傷者10,000以上を出す激戦のすえ、第三軍は12月4日に203高地を占領し、ロシア軍は戦力を決定的に消耗した。その後第三軍は要塞東北正面の堡塁群を攻略し、1905年1月1日に旅順要塞司令官ステッセル中佐は降伏した。
沙河では両軍の対陣が続いていたが、ロシア軍は新たに前線に着任したグリッベンベルク大将の主導のもと、1月25日に日本軍の最左翼に位置する黒溝台方面で攻勢に出た。一時、日本軍は戦線崩壊の危機に陥ったが、秋山好古少将、立見尚文中将らの奮戦により危機を脱した。2月には旅順攻略を完遂した第三軍が戦線に到着した。
日本軍は、ロシア軍の拠点・奉天へ向けた大作戦を開始する。2月21日に日本軍右翼が攻撃を開始。3月1日から、左翼の第三軍と第二軍が奉天の側面から背後へ向けて前進した。ロシア軍は予備を投入し、第三軍はロシア軍の猛攻の前に崩壊寸前になりつつも前進を続けた。3月9日、ロシア軍の司令官クロパトキン大将は撤退を指示。日本軍は3月10日に奉天を占領したが、またもロシア軍の撃破には失敗した。一連の戦いで両軍とも大きな損害を受け作戦継続が困難となったため、その後は終戦まで四平衛付近での対峙が続いた。
日本海海戦・講和へ
戦争の決着をつけたのは海戦であった。バルト海沿岸を本拠地とするロシアのバルチック艦隊は、旅順(旅順陥落の後はウラジオストク)へ向けてリエパヤ港を出発し地球を半周する航海を続けてきたが、5月27日から5月28日の日本海海戦において、連合艦隊は東郷平八郎司令長官の良き司令によってバルチック艦隊に完勝した。この結果、日本側の制海権が確定した。
ロシアでは、相次ぐ敗北と、それを含めた帝政に対する民衆の不満が増大し、1905年1月9日には血の日曜日事件が発生していた。日本軍の明石元二郎大佐による革命運動への支援工作がこれに拍車をかけた。日本も、当時の乏しい国力を戦争で使い果たしていた。両国はアメリカ合衆国の仲介の下で終戦交渉に臨み、1905年10月に締結されたポーツマス条約により講和した。
日本は19か月の戦争期間中に戦費17億円を投入した。戦費のほとんどは戦時国債によって調達された。当時の日本軍の常備兵力20万人に対して、総動員兵力は109万人に達した。戦死傷者は38万人、うち死亡者8万7,983人に及んだ。さらに、白米を主食としていた陸軍の野戦糧食の不備により、脚気患者が25万人、病死者は2万7,800人に上った。
 |
日独戦争
大正3年8月23日~大正7年11月11日、第一次世界大戦に於ける大日本帝国とドイツ帝国の戦争。
日本は日英同盟に基づき連合国の一員として参戦した。1914年8月23日大日本帝国はドイツ帝国へ宣戦布告。陸軍はドイツが権益を持つ中華民国山東省の租借地青島を攻略、海軍は南洋諸島のドイツ要塞を次々に攻略し、第一次世界大戦終結とともに日本が勝った形で終結した。
大正3年(1914年)8月1日 欧州に世界大戦が勃発した。当初我が国は厳正中立を表明するも、英仏など連合国からの支援要請を受けてドイツに宣戦を布告するに至った。 日本の参戦理由は日英同盟に根本をおいたものであり、宣戦の詔勅にも明示されていたが、日英同盟は必ずしも日本の参戦を義務づけるものではなかった。欧州大戦を好機ととらえ、世界における日本の地位を高め東亜における立場を強固にしようとしたので。即ち、渋滞を極めていた支那問題を解決して東洋平和を確立することを目的としたもので、日露戦争までが国家存亡の関頭にたってやむなく受けて起った戦争であるのに対し、この日独戦争は、国策遂行の手段としての戦争であるとも見られるものであった。
欧州列強が死闘を継続している間に米国と日本は急速に国力を伸長した。とくに日本の発展はめざましく、五大強国の一つと云われ新設された国際連盟の常任理事国を勤めるまでになった。しかし日本の主張した人種差別撤廃宣言は容れられることはなく、日英同盟は破棄され、やがては日本の発展を阻止せんとする対日圧迫政策を招来することとなった。
サラエボ事件
大正3年(1914年)6月28日 オーストリア=ハンガリー帝国の皇太子フランツ・フェルディナンド大公は、ソフィー・シュテック妃殿下と共に、ボスニア州で挙行される陸軍大演習の統監に赴く途中、州都サラエボの市役所に立ち寄った。晴天の日曜日とあって沿道は皇太子夫妻を歓迎する人波で埋め尽くされていた。その時一人の男が市役所の歓迎式典に向かう自動車に向かって爆弾を投げつけた。爆弾は後続車の前で爆発、侍従武官と副官、群集の数人が負傷した。
あやうく難をのがれた夫妻は、それでも予定どおり歓迎式典に臨んだ後、危険を避けるために帰路を変更、川沿いの道を進むことにした。しかしこの予定変更は上手く伝わらなかった。先導車輛が元のコースを進もうとしたため改めて車をバックさせようとしたその時、一人の青年が拳銃を発砲、最初の一発は皇太子の顔に、二発目は皇太子妃の腹部に命中した。直ちに二人は手当てのため運ばれたが15分後には死亡した。
最初に爆弾を投げた工員も拳銃を発射した19歳の学生もセルビア人であった。取り調べの結果この事件は、汎スラブ主義秘密結社による組織的な暗殺計画に基づいて決行されたもので、本拠はセルビアの首都ベルグラードにあり、背後にはセルビア軍部が関与していることが明らかとなった。
ではどうしてオーストリアの皇太子がセルビアの青年に撃たれなければならなかったのか?そこには「ヨーロッパの火薬庫」バルカン半島を巡る各国の複雑な対立があった。
バルカン半島情勢
バルカン半島は古代ギリシャ、ローマの文明が栄えた文化の地であるが、中世に入ってオスマン・トルコ帝国の領土となり、ながくその圧政に苦しんでいた。19世紀に入り、民族解放運動に刺激されてバルカンの諸民族はトルコからの独立を要求、やがてその支配から離れて、ギリシャ、ルーマニア、ブルガリア、セルビアの諸民族はそれぞれ独自の国家を形成するに至った。このうちセルビアはアドリア海にのぞむモンテネグロ、ボスニア、ヘルツェゴビナの三州を併合、大セルビア国をスラブ民族の手によって建設しようという希望を持っていた。
この動きを支援していたのが同じスラブ民族国家であるロシアであった。ロシアはコンスタンチノーブルを勢力下におくための手段としてバルカン諸民族の庇護者を標榜し、その民族解放運動を支援することによってトルコ帝国の分断を図っていた。ロシアとトルコの紛争は明治9年(1876年)以降武力紛争に発展、露土戦争となった。明治11年(1878年)にサンステファノ条約によって一旦終息したものの、あらためて激化したバルカン情勢の調停を協議する7ヶ国ベルリン会議が開かれた。これによってボスニア、ヘルツェゴビナの二州はオーストリアが委任統治の形で行政権を預かることとなった。
ところが明治41年(1908年)になり、オーストリアは自国領として併合してしまったのである。併合されたセルビア人住民はもちろん親国たるセルビアも怒って武力によってでもオーストリアから奪還しようと考えた。しかしオーストリアの背後には同盟国ドイツ帝国が控えている。一方のセルビアの後ろ盾となるロシアは、日露戦争の敗戦(明治38年1905年)の痛手から立ち直るには時間を要する。機会をうかがうこと数年、サラエボの銃声はセルビア人の積年の恨みがこめられていた。
台頭するドイツとロシア・イギリスとの対立
「サラエボ事件」が欧州大戦の契機ではあったが、その遠因は二大陣営の対立に端を発する。
ウイルヘルム1世を擁し、ビスマルク、ローン、モルトケの三傑の指導するプロシアは、普墺戦争、普仏戦争を経て明治4年(1871年)近代国家としての統一ドイツ帝国を完成させた。その後19世紀末には飛躍的に国力を増強させ、ウイルヘルム2世によってフランスに代わって欧州第1の強国になった。それどころか生産力はイギリスをも凌ぎ、独商品は世界的に英商品を駆逐しつつあった。しかし近代国家としての発足がおそく、列強各国に比べる植民地獲得競争に立ち遅れていた。
ドイツは同じゲルマン民族の多いオーストリアとは同盟関係にあった。そのオーストリアがバルカン方面でロシアと対立することを恐れ、ロシアの関心を極東方面に向けさせようとしていた。日露戦争後の三国干渉はその典型である。
ロシアの伝統的南下政策には、元来3つのルートが存在していた。
1、バルカン半島・ダーダネルス海峡経由の地中海進出
2、中央アジアからイラン・アフガニスタン経由のインド洋進出
3、支那東北部(満州)、朝鮮・ウラジオストク経由の日本海進出
いずれのルートにおいてもロシアはイギリスと利害が衝突しており、その上近東でオーストリア、極東では日本とも激突することとなった。19世紀末からの満州や朝鮮でのロシアの南下政策はとくに活発であったが、日露戦争での日本の勝利は、極東方面に主力を注いでいたロシアの南下政策に変更を余儀なくされた。以降ロシアは、南下政策の重点を極東からバルカン方面に移さざるをえず、ここにロシア-オーストリア両国の衝突は必至となった。
三国同盟と三国協商
明治11年(1878年)の7カ国によるベルリン会議によってロシアとの間に不和が生じたドイツは、オーストリアと結んでロシアに備えることとなった。さらに植民地問題でフランスと不仲となっていたイタリアを含め、明治15年(1882)5月 ドイツ、オーストリア、イタリアによる三国同盟が成立した。
三国同盟によって脅威を受けたロシアは、同様に脅威を感じていたフランスに接近、明治24年(1891年)両国の間に秘密同盟が締結された。イギリスは欧州大陸でのバランス・オブ・パワーを保つことを外交の基本としており久しく中立を保っていたが、ドイツが強力な軍備を背景に次第に台頭してくると、植民地問題で不和になっていたフランスと結んで明治37年(1904年)英仏協商を成立させた。次いで日英同盟から日露戦争以来悪化していたロシアとの関係を改善して、明治40年(1907年)イギリス、フランス、ロシアによる三国協商を成立させた。
これから欧州大戦の勃発する大正3年までの7年間は、この三国同盟と三国協商との二大陣営の対立がつづくのである。
この三国協商は最終的には「ドイツ封じ込め政策」であった。ドイツと三国同盟を結んでいるイタリアですら、ドイツと結んでいる限り英仏の圧迫を受けてことごとく不利になるので、むしろ三国協商側に同調する気配を示していた。ドイツの頼みとするのは結局オーストリアだけである。しかし、神聖ローマ帝国の余光で国勢を保ってはいるものの、皇太子を暗殺され失意の底にある老齢のフランツ・ヨセフ1世が死去したら、多民族国家である墺は自壊する危険性があった。墺にとっても、自国の版図を拡大するにはバルカン半島への進出以外に道はなく、それにはセルビアを中心とする汎スラブ民族主義運動と、背後に控えるロシアが大きな障壁となっていた。
欧州各国の参戦
緊迫するバルカン情勢においてドイツとの緊密な連携を準備していたオーストリアにとって、サラエボ事件は決定的なものとなった。予めドイツの同意を取り付けていた墺は、7月23日10か条からなる強硬なる最後通牒をセルビアに手交、事態は一気に緊張の度を強めた。墺のセルビアに対する戦意は明白で、事件が拡大するか否かは、セルビアを支持するロシアと墺の背後にあったドイツの態度如何にかかっていた。三国協商の一翼である軍事大国ロシアは、墺に向かってロシア-オーストリアの二国間協議を提議したが28日 墺はこれを拒否してセルビアに宣戦布告した。
一方ドイツは、本件を墺とセルビア間に限定されたものとして考え、セルビアを支持してロシアが起つとまでは予想していなかった。その上イギリスは中立を守るであろうことを期待していた。駐独英国大使に向けて「ドイツが限定的参戦の場合、イギリスの中立」を要求した。しかしイギリスは29日、問題が独、仏を巻き込む場合、英の参戦の可能性を言及、事件拡大を強く警告した。非公式ながらも英国の強硬な態度表明は独政府に大きな衝撃を与えた。ドイツは再度、墺とロシアとの二国間交渉を強く勧告するも状況は遅きに失した。
7月30日 ロシアの総動員は最後的に発令された。
ロシアの総動員令をもって事態は一挙に世界戦争への道を辿る。セルビアに対してのみ動員を準備していた墺は、ロシア戦を想定し改めて総動員を準備、ドイツも総動員が必至となり、8月1日ドイツはロシアに宣戦した。同時にロシアと同盟関係にあるフランスに向かって、独露開戦の場合の仏政府の態度を8月1日迄に回答せよと要求した。フランスは「国家の利益の命ずるところに従う」と返答、国境付近での挑発的行動が続いたのち、8月3日仏軍がベルギーの中立を侵犯したことを口実に、ドイツはフランスに宣戦した。またベルギーに対しては軍隊通過を要求する最後通牒を提出、永世中立国のベルギーは敢然とこれを拒絶し、アルベール国王は正義のために戦うことを国民に宣言した。こうなると三国協商の最後の一国、イギリスの態度はもはや明白であった。ドイツのベルギーの中立侵犯が明らかとなった4日夜、ドイツと戦争状態にあることを宣言した。
ドイツの東亜進出
ドイツが世界的殖民政策を開始したのは、1870年の普仏戦争(プロシャ・フランス戦争)以降において自国の基礎が固まってからのことである。上述のように当時、すでに先進国である英仏などによって有望な植民地の分割は終わっていたので、僅かにアフリカのトーゴー、カメルーンと南洋諸島を得たのみであった。東亜においては以下のとおりである。
明治17年(1884年) ソロモン諸島
明治18年(1885年) マーシャル諸島
明治32年(1899年) サモアの一部、南洋諸島
そこでドイツは支那に着目し、日清戦争後進んで三国干渉に加わり、遼東半島還付に関して恩を清国に売るとともにロシアに接近し、明治30年(1897年)11月、山東省でのフランツ・ニースとリヒァルト・ヘンレの二名のドイツ人宣教師が中国人によって殺害される事件にかこつけ、直ちにドイツ東洋艦隊は軍艦を派遣して膠州湾の占領を狙い、明治31年3月には膠州湾条約によって、清国から正式に膠州湾を99年間租借することに成功した。かねてより同湾に着目していた著名な地理学者リヒトホーフェンの報告もあり、ドイツはここに大築港を行い軍港を設け、軍事上、経済上の根拠地とした。この他山東省内において鉄道施設権、鉱山採掘権を得、次いでその勢いは北清一帯にも及び、さらには揚子江流域にも及んで日英両国にとって脅威となっていった。
対独参戦を巡る日英折衝
大正3年8月1日 イギリスのエドワード・グレー外相は駐英大使井上勝之助に対し、「もしイギリスが仏露側にたって参戦するとしても、英日同盟にかかわる諸利益が巻き込まれることがあるとは考えないし、英国政府が日本政府に援助を求める事態を想定してもいない」と語っていた。之に対し時の大隈内閣は、イギリス参戦の報を受けていない8月4日に「帝国政府は戦局が波及せざらんことを望み、かつ帝国政府は厳正中立の態度を確守し得べきことを期待するものなり。然りと云えども日英同盟の危殆に瀕する場合に於いては、協約上の義務として必要なる措置を執るに至ることもある。」との立場を表明していた。
しかし英国側は対独戦必至となるや、日本の限定的参戦を希望するようになり、グレー外相は駐日英国大使グリーンに対し、「戦争が極東に波及する場合、英国政府は日本政府に助力を依頼する」旨打電した。英国は支那におけるドイツ租借地を日本が奪取して大陸の権益を増大させることを望んでいない一方で、極東での英国支配地確保のためには日本を利用しようという虫のいい期待を持っていたのである。
8月7日 英独開戦後、独艦艇による海上貿易が脅威を受けるに従い、グリーン大使はグレー外相の覚書を加藤高明外相に提出、日本の参戦を正式に希望する。これを受けて大隈内閣は緊急閣議を開いた。消極論が一部から出されたが、「会議の空気は参戦に勝る外交上の良策なしに傾き、之は同盟に拠る義戦であると同時に三国干渉に対する復讐戦である」として、参戦を是認した。8月8日 1800 山縣有朋ら元老を加えた重要閣議が官邸で開かれた。前夜の閣議以上に強い懸念論が元老の一部から出されたものの大隈首相と加藤外相の説得が功を奏し、英国からの援助依頼を渡りに船とした日本は、電光石火で参戦を決定したのであった。
日英両国の思惑
英国の本心は、「英国の権益保護のために日本に参戦して欲しい。ただし、日本の権益が拡大されない限りにおいて。」である。そのため日本には限定的な対独宣参戦-シナ海を越えて太平洋まで拡大されず、ドイツ占領下の領土を除き他国の領土にも拡大されない-のみを希望していた。
しかし日本側には、作戦行動をイギリスの云う「一定水域での海軍の軍事行動」に限定する意志はなかった。8月9日 加藤外相はグリーン英国大使に対し、戦争行為の範囲に制限をつけることに反対し、イギリスの利己的な限定軍事行動要請に対して、参戦の大義名分は日英同盟の履行に置いていることを伝えた。これを受けたイギリスは10日、無制限的軍事行動を警戒して「帝国(日本)政府ニ於テ軍事行動ヲ見合セラレ度」と、参戦要請を撤回してしまった。
だが日本としても国策として一旦決定した参戦方針を取り消すことはできない。加藤外相は、「戦地を限定することを布告中に声明することはできないが、英国政府が希望するなら同様の証言を英国若しくは関係国に与えることに異議はない」とし、イギリスも「強いて宣戦布告中に戦地局限を記載する必要はないが、日本政府から領土侵略の野心がないことを保証されれば英国政府は納得する。」と譲歩した。こうして日英両国間の相互譲歩の結果、ようやく日本の対独参戦が決定したのである
このように一度は日本に対する参戦要請を撤回したイギリスも、のちには本格的な戦争協力をくりかえし要請することになる。
対独墺 最後通牒
8月15日、一週間後の8月23日正午迄に無条件に応諾するよう対独最後通牒を発した。具体的要求は以下の2項目である。
1) 日本及び支那海洋方面からの独艦艇の即時退去。退去できない独艦艇は武装の解除
2) 膠州湾租借地全部を支那に還付する目的を以って1914年9月15日を限り、無条件にて日本に交付
加藤外相は同日、在日仏露米各国大使とオランダ、支那両公使に対し、此の機会に領土を拡張する野心は存在しないことを説明し了承された。しかし日本の軍事行動に不安を感じていた英国は17日「日本の行動は、支那海を越えて太平洋まで拡大されることはなく、支那海以西のアジア水域や独領土以外の外国領土まで及ぶことはないと了解している。」との声明を日本に無断で発表した。日本政府を憤慨させつつも日本の軍事作戦を牽制した。8月23日に至るもドイツ側からの回答はなかった。同日対独宣戦の詔勅が煥発せられ、対独戦に参加することとなった。
対オーストリア関係についても問題となった。両国間には紛争の種はほとんどなかったが、駐日オーストリア大使は27日、本国から日本退去の訓令を受けた。これを受けて日本側も在墺大使に引き揚げを打電、ここに日墺両国の外交関係は断絶し、事実上の戦争状態となった。
青島要塞の兵備
青島は明治24年(1891年)以来、清国北洋艦隊の基地となっていた小都市であった。明治31年(1898年)、膠州湾地域がドイツの手にうつると青島はドイツ東洋艦隊の根拠地となり、近代的港湾施設が整備され、欧州的な大都市として上海、天津につぐ支那第三の貿易港に生まれ変わっていた。
青島要塞の前進陣地は、臨時築城の狐山から浮山に至る線で、簡単な散兵壕と砲兵陣地を設けていた。
第一防御線は海泊河口左岸から小湛山東方にわたる線で、5つの永久堡塁が設けられていた。これらの各堡塁は深さ約10M、鉄条網をもって囲まれ、それぞれ数百からの守備兵からなっていた。第二防御線は、モルトケ山~ビスマルク山~イルチス山にわたる線で、陸正面に対する砲台として13の大、中小口径の永久砲台、海正面に対しては、28センチ砲4門をはじめとする18門、5個の大型砲台があり、このうちの3砲台は陸正面にも使用可能であった。これらの堡塁の前に延々4キロに及ぶ大鉄条網を張り巡らし、外壕は高さ6・7メートルに及んだ。
この他、艦艇から陸揚げされた火砲、人員もあって防御設備は強化されつつあり、11月の要塞開城時点でなお半年の篭城に耐え得るだけの諸物資を蔵してはいたが、備砲の多くは旧式で、本国から遠く離れた青島要塞も所詮は孤立無援であった。
日本軍は大兵力を動員しており、彼我の戦力は格段の相違があり勝敗は初めから明らかであったと云えよう。
青島要塞の包囲戦攻略準備作戦、
大正3年8月23日 ドイツに対して宣戦が布告されると、まず第一艦隊は主力をもって黄海から東シナ海北部にわたり敵艦の捜索と警戒、第二艦隊は独租借地である膠州湾を封鎖した。海軍の活動開始と相前後して参謀本部は、久留米の第18師団に動員令を下し、師団長神尾光臣中将を青島要塞攻囲軍司令官に、山梨半造少将を参謀長に任命、8月25日から逐次出発を開始した。
9月2日 海軍陸戦隊の先導のもと、山田支隊が豪雨をついて龍口に上陸、師団主力も引き続き上陸を始めた。連日の暴風雨とそれに続く洪水や悪路に妨げられながら前進したが、糧秣の輸送が続かず、神尾中将も兵卒と同一の食事を採りつつ前進を続けた。上陸当初は若干の敵斥候兵と遭遇する程度であったが、、南進とともに敵兵の数は増え、火砲機関銃をもった数百の独兵と交戦するまでとなった。9月25日 師団主力は妨害を排除しながら前進集結を終了、後方補給も整頓されつつあった。
9月26日 師団主力が流亭に到着、攻撃前進を決定し青島攻囲戦を開始した。堀内支隊(歩兵第46聯隊を主力とする第23旅団)は大した抵抗を受けることもなく南龍口東方高地に進出、27日正午には、師団は李村河口から金家嶺付近に至る線を占領、28日には、青島要塞前進陣地である狐山から浮山に至る線への攻撃を開始するに至った。要塞攻撃には不向きの騎兵聯隊は膠州から西南に進撃し、膠州湾の対岸に散会して膠州湾全域を掌中にした。この間、膠州湾の墺巡洋艦「カイゼリン・エリザベット」を中心とする艦艇による海上からの側面攻撃を受けて大いに苦戦したが、青島要塞は、第二艦隊による海上封鎖とあいまって日本軍によって全面包囲された。
非戦闘員の退去
10月2日の四房山の戦闘は激烈を極めた。岩切見習士官以下の1個小隊の前哨に対し、奪還しようとするドイツ軍の執念はものすごく、約3個中隊が砲兵援護のもとに逆襲してきた。日本軍はドイツ軍の動きを察知して迎撃態勢をとっていたが、再度の敵襲に弾薬を使い果たし、戦死5、負傷6を出した。ドイツ軍は病院自動車で死傷者を収容していたが、なお死体の多くが残っていた。
日本軍は電信を使ってドイツ兵の死体収容についてドイツ側と交渉中であったが正式に日本軍にその処置を依頼してきた。このため10月12日から休戦状態となり、死体収容が開始された。また非戦闘員と中立国人の生命を憂慮される勅旨が届いたので、神尾中将、加藤第二艦隊司令長官の連名でドイツ側に伝達、ただちにドイツ側より丁重な回答があり、13日から磯村大佐とカイゼル海軍少佐の会見によって詳細が決められた。
非戦闘員受け渡しの内容は日露戦争時の旅順攻囲戦で行ったものとほぼ同じ内容であった。日本の瑞宝章を受けていたカイゼル少佐は礼儀正しく、別れる時には黒見で戦死した玉崎中尉の遺品を磯村大佐に手渡した。非戦闘員は海路によって受け渡されることになり、15日 退去者の受取人としてドイツ語のできる山田大尉がドイツ側ランチを迎えた。ドイツ軍使はベヒテスハイム海軍大尉で、奇しくも伊集院大将が独キール軍港を視察した時の案内担当者であった。ベヒテスハイム大尉はドイツ総督からの感謝の言葉を伝え、退去者の移乗が終わるとドイツのランチは静かに去っていった。日本軍は喇叭手が「別れの曲」を吹奏、両軍は互いに帽子やハンカチを振って別れを惜しんだ。
青島攻防戦の間に所在していた非戦闘員は約1300名、このうちドイツ人は約500名であった。
青島要塞総攻撃
日本軍は浮山から狐山の線を占領後攻略準備を着々と進め、10月29日に全軍行動を開始、天長節(大正天皇誕生日)の10月31日、海軍重砲隊の砲撃開始とともに、全砲兵、海軍艦艇も呼応して総攻撃が開始された。
我が総攻撃が近いことを察知したドイツ軍は、ビスマルク砲台から第1、第2中央隊の後方に猛烈な射撃を集中、第一線に対しては機関銃・軽砲を夜間まで猛射しつづけた。青島大港の造船所に続き大港東端の石油タンクから黒煙が天高くあがった。これはドイツ軍自身による放火とされており、神尾司令官は戦闘と無関係な放火に対して警告文を送った。このあいだにも第一線部隊は前進を続け、11月1日夜までに第一攻撃陣地の占領を終わり、第二攻撃陣地に向かって攻撃を続行した。
膠州湾にあった墺巡洋艦「カイゼリン・エリザベット」の攻撃は最後まで激しく日本軍の右翼隊を悩ませていたが、正木中佐の指揮する海軍重砲隊がこれに応戦して沈黙させ夜になって自沈した。11月3日には第二次攻撃陣地を占領、翌4日には第三次攻撃陣地への前進作業に主力を注ぎ、砲兵は主力をもって堡塁を、一部をもって砲台線と青島市街を砲撃した。特にこの日午後からの28センチ榴弾砲の威力は大きく、市街発電所に命中したため青島全市街は停電し闇夜と化した。一方でドイツ軍の猛射もすさまじく、我が攻撃前進は困難になってきた感があった。しかし11月5日になると、前進部隊は次第に敵の堡塁下に迫り、中には外壕の斜面に達して突撃路の掘削を開始する部隊もあった。各地区隊は11月6日までにほぼ第三次攻撃陣地を構築、突撃準備を整えた一方で砲兵は砲撃を開始した。敵飛行機は同じ頃、青島を脱出して上海方面に去っていた。
11月7日、第二中央隊左翼部隊が中央堡塁を占領、同右翼隊と左翼隊が台東鎮東堡塁と小湛山北堡塁を占領、以下次々と敵陣を陥落させ、海岸堡塁が降伏した。この間ドイツ軍はいくつかの砲台を自爆させ、気象台に白旗を掲げ軍使を派遣、会見ののち開城の通告を行った。
大正3年(1914年)11月7日 青島要塞は陥落した。 11月16日には青島入城式と招魂祭を行い、ここに青島要塞攻略戦は完全に終結した。
南洋諸島占領と独東洋艦隊の潰滅
開戦と同時に膠州湾を脱出したドイツ東洋艦隊は南太平洋に出没し、しきりに海上通商を妨害していた。このため大正3年(1914年)10月 日英海軍協同作戦協定が成立、第一、第二南遣艦隊と南北アメリカ沿岸派遣隊を出動させた。
これに先立ち、9月29日には独根拠地の一つであるヤルート島を砲撃ののち、陸戦隊によって無血占領した。これに続き10月19日までにサイパン島をはじめとする赤道以北の独領南洋諸島をすべて占領した。
洋上では、ホノルルに入港していた独砲艦「ガイエル」を日本艦隊が港外に待ち構えて武装解除を支援した。11月1日に英戦艦「グッドホープ」以下2隻の巡洋艦と遭遇、「ブレーメン」「ライプチヒ」の2隻を失っていたドイツ艦隊は、南米海域にあった。日本の第一南派遣支隊は、英戦艦「カーパス」「カーナボン」などとともにアルゼンチン南東沖で待ち伏せ、12月8日には「シャルンホルスト」「グナイゼナウ」「ニュールンベルヒ」「ドレスデン」の4隻を撃沈した。
インド洋を中心に神出鬼没な行動で通商破壊活動を行っていた独巡洋艦「エムデン」も、英巡洋艦「シドニー」によって擱座させられており、12月8日をもってドイツ東洋艦隊は全滅した。
 |
尼港事件(にこうじけん)
シベリア出兵中の大正9年(1920年)3月から5月にかけて、ロシアのトリャピーチン率いる露中共産パルチザン(遊撃隊)によって黒竜江(アムール川)の河口にあるニコライエフスク港(尼港)の大日本帝国陸軍守備隊及び日本人居留民が無差別に虐殺された事件。
パルチザンに対して一旦降伏した後、大日本帝国陸軍側が再度攻撃して敗北。生き残った日本人は軍人であるか民間人であるかを問わず捕虜とされた。そして、5月に日本陸軍がニコライエフスクへ援軍を送るやパルチザンは全ての捕虜を殺害した上で逃亡した。また、日本人以外の市民も殺害した上、町を焼き払った。
後にこのパルチザンの責任者はソビエト連邦政府により死刑になった。この事件による日本人犠牲者は約700名に上り、その半数は民間人であったため、国内世論は憤激の声が渦巻き、反共機運が強まり、後々まで尾を引くことになった。日本陸軍がシベリア出兵を延長したのは、この事件によるものという見方もある。
この過激派軍は、赤軍系パルチザンと韓人教師朴エルリアが組織した「サハリン部隊」とが連合したものであった。
 |
| 1900年の尼港 |
<参考文献>
菊地明(他)編, 『戊辰戦争全史』〈上・下〉, 新人物往来社
陸奥宗光 中塚明 校注 『蹇蹇録』日清戦争外交秘録 新訂ワイド版岩波文庫255 岩波書店
デニス・ウォーナー、ペギー・ウォーナー(著)、妹尾作太男・三谷庸雄(共訳)『日露戦争全史』、時事通信社
斎藤聖二, 『日独青島戦争』, ゆまに書房
『太平洋戦争の謎 魔性の歴史=日米対決の真相に迫る』佐治芳彦 大日本帝国文芸社
斎藤充功『昭和史発掘 開戦通告はなぜ遅れたか 』新潮新書 新潮社
『八月十五日の神話 終戦記念日のメディア学』佐藤卓己 筑摩書房
<ページ引用>
ウィキペディア・フリー百科事典
近代日本戦争史概説
文責
的場 宣明
昭和12年2月生